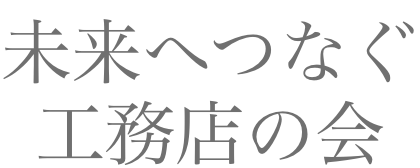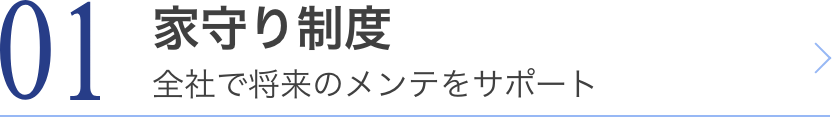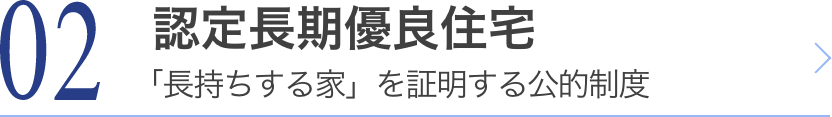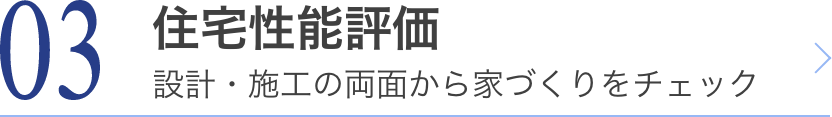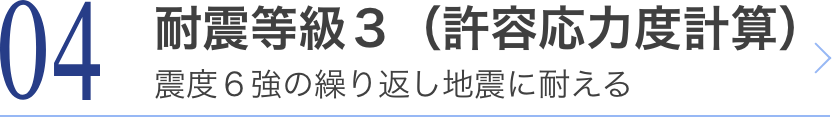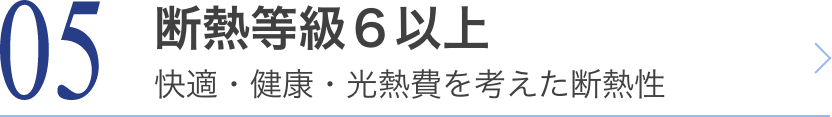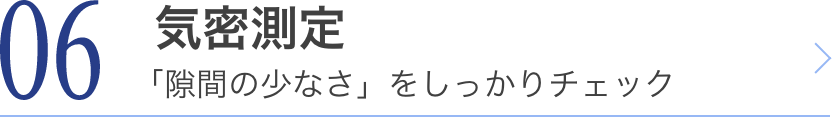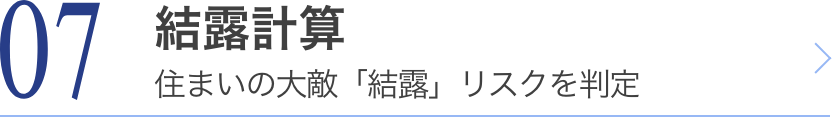「最高等級」は最低基準
日本の現行法では、耐震性能は等級1、2、3の三段階で表されます。
よくある説明としては、建築基準法レベルが等級1。
その1.25倍の耐震性を持つのが等級2で、1.5倍の耐震性を持つのが等級3と言われます。
災害時の対策拠点となる消防署や警察も耐震等級3ですから、それだけ強固な性能ということなのですが、
でも、これってちょっと分かりづらいと思いませんか?
もっと簡単に言うと、
耐震等級1
震度6強~7の地震(数百年に一度レベルの大地震)でも倒壊しない。
躯体は損傷する可能性が高く、半壊程度の被害は起こりうる。
内外装にダメージがないように見えても、被災後に点検や補修・補強をせずそのまま住み続けることはリスクが高い。
耐震等級2
震度6強~7の地震でも倒壊せず、躯体の損傷も比較的少なくて済む。
耐震等級3
震度6強~7の地震ではほとんどの損傷を防ぎ、被災後もそのまま住み続けられる可能性が高い。
このような差があります。
三つの等級は、「大きな地震でも倒壊せず、住まい手の命を守る」という意味では共通しています。

しかし、これはあくまで地震が一度きりだった場合の話。
2016年に起きた熊本地震では、4月14日に震度7の前震が起きた後、二日後の4月16日にも震度7の本震が発生しました。
それ以降にも震度6弱や震度5強の強い余震が繰り返されることで、前震では崩れなかった耐震等級2以下の建物が多数倒壊しています。
繰り返し起きる大地震に対して、前述した定義は当てはまらないわけです。
一方で、耐震等級3で建てた住まいは、それらの群発する大地震にも耐え一棟も倒壊していません。
現地調査によれば、等級3の建物は、軽微な損壊と小破が1棟ずつ見つかっただけだと言います。
(参考:一般社団法人くまもと型住宅生産者連合会資料)
それに、倒壊による人的被害は避けられても、その後、我が家に戻ることができないのはQOLが下がります。
火災保険の地震特約でも、建て替えや修繕費用の全額が出るわけではありませんから、もし手元資金に余裕がなければ、
① 住宅ローンを払い続けながら、家賃を払って借家に住む
② いつ終わるともしれない避難所生活を続ける
このような選択肢しか残されていません。
これはあまりにも辛い体験です。
地震大国日本において、とりわけ私たちが暮らす地域は、南海トラフ大地震も予見されています。
過去の歴史から学ぶなら、耐震等級3以外は「ありえない」と言い切ってもよいでしょう。
許容応力度計算って?
耐震等級3を実現するにあたり、合わせて実施しなければいけないのが許容応力度(きょようおうりょくど)計算。
現状の一般的な建物設計では「仕様規定」というルールが用いられています。
これは、建物の部材や材料が一定の基準を満たしていれば、安全な建物と見なされるという考え方です。
例えば、
「この大きさの木材や鉄筋を使いなさい」
「この高さの建物には、これだけの壁の厚さや量が必要です」
といった、標準的なルールに従うことを要求します。
しかし、これはあまりにも雑な基準。
建物の重さに耐えられる構造材なのか、
地震が来た時にどれだけの外力に耐えられるのか、
などをしっかり計算しているわけではないのです。
耐震等級3を取得しても、それが「仕様規定」によるものでは信頼性に劣るということですね。

一方で、建物の強度を厳密に算出するのが「許容応力度計算」。
材料や部材一つひとつの強度を洗い出し、それらを総合して、どれだけ外力に耐えられるかを評価する手法です。
耐震等級3は、許容応力度計算がセット。そう覚えておきましょう。
「耐震等級3相当」に注意
耐震等級は、住宅性能表示や長期優良住宅の認定の際に、書類に明示されるべきもの。
そうでなければ、対外的にあなたの住まいが「耐震等級3」である証明ができません。
しかし、たまに見かけるのが「耐震等級3相当」という表記。
これは「耐震等級3と同じレベルで設計をしていますよ」という建築業者さんのPRなのですが、これを鵜呑みにしてはいけません。
いくら構造的に優れていても、それが証明されなければ、あなたの住まいは耐震等級1と一緒。
将来的な資産価値も、相応に下がります。
それに、もし等級3のレベルで耐震性を担保できているなら、証明した方がよっぽどおトク。
耐震等級3であれば地震特約も半額になりますから、「相当」とうやむやにするのは非常にもったいないことなのです。
「耐震等級3相当」と謳う業者さんは、実際には耐震等級3のレベルに達していないと思ってもよいでしょう。