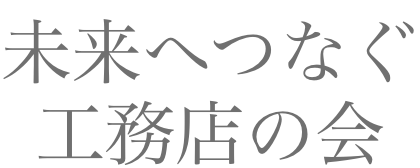断熱性能と対をなす「気密」
たとえ、高性能で高耐久な断熱材をふんだんに使ったり、優秀な空調換気システムを使っていても、家の隙間が大きければすべて台無し。
隙間から外の寒い空気が入ってきたり、温めた室内の空気を逃がしてしまうからですね。
「高断熱・高気密」と世に言われているように、断熱と気密はセットで考えなければいけないもの。気密性能はどのように判断すべきかチェックしておきましょう。
C値とは?
C値とは、住宅の延床面積1㎡あたりに相当する隙間面積(㎡)を表す指標です。具体的には、家全体の隙間面積(㎡)を延床面積(㎡)で割った値で、単位は「㎡/㎡」で表されます。
例えば、C値が1.0という場合、延床面積1㎡あたりに1㎝の隙間があることを意味します。数値が小さいほど隙間が少なく、気密性が高い住宅であることを示します。
一般的に、C値1.0以下の建物を高気密と呼びます。高断熱であることが前提ですが、C値が良いと、エネルギーロスが少ないため、冷暖房にかかる光熱費も最小限に、快適な空間を生み出すことが可能です。
気密性能は「施工精度」が命
先に述べたように、設計時にどれだけ高性能な断熱材や空調換気設備を採用しても、気密性能が低ければ意味がありません。

断熱性能は、使う材料を元に設計時に計算ができるものですが、気密性能は「いかに隙間なく施工できるか」という職人さんの作業の精度がすべてです。
壁を貫通する配管や電線の隙間を適切に埋めたり、窓枠と壁の接合部分をきちんと処理したり、構造材やパネル同士をピッタリ合わせたりという、細やかな配慮がものを言うのです。
結露にも注意が必要
気密性能が低い住宅では、室内外の空気が隙間を通じて自由に出入りしてしまいます。そして、それによって結露を引き起こされるわけですね。
例えば、冬場、室内の暖かい空気が隙間を通じて外気に触れると、急激に冷やされて水滴が発生します。
逆に、夏場は冷房された室内の冷気が外の暖かい空気に触れることで結露が生じることもあります。
特に問題となるのが、壁の内部で発生する結露。カビや腐朽菌が繁殖しやすく、構造材を劣化させる原因にもなりかねません。室内の空気環境も悪化するため、喘息やアレルギーなどを引き起こすこともあるでしょう。
住宅の長寿命化や住まい手の健康を守るなら、気密性能を高めて結露リスクを減らすことも必須のこと。ぜひ気密性能の高い住まいを選びましょう。
「気密測定」が必須の理由
建物の隙間量を特殊な機械を使って計測するのが「気密測定」。
気密性の良し悪しは施工品質次第。つまり、ただ作っただけでは、実際の性能は分かりません。だからこそ、実際に計測することが重要です。
未来へつなぐ工務店の会では、所属する工務店には「全棟で気密測定すること」を定めています。
お客さまに対し、誠実なかたちで性能を証明することは、これからの家づくりで必須のことだと、私たちは考えています。