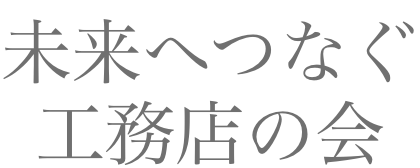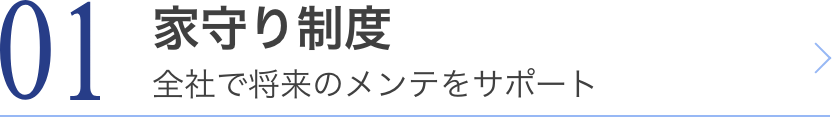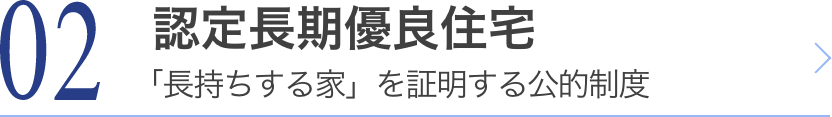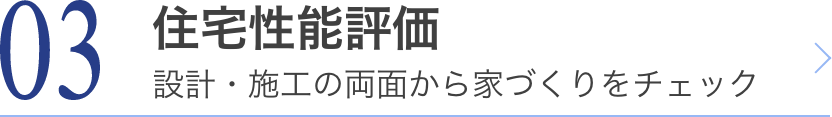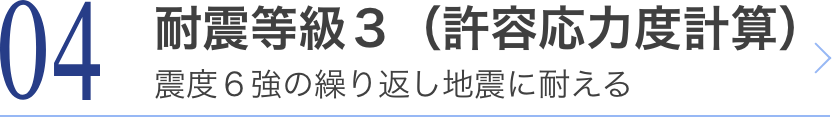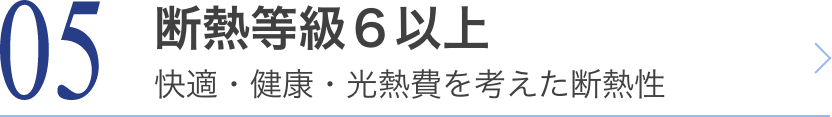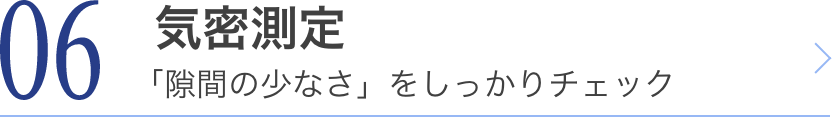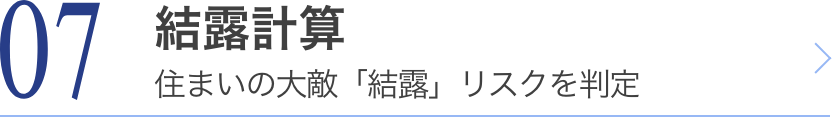長期優良住宅とは?
長期優良住宅制度は、簡単に言えば「長持ちする住宅」のこと。国土交通省が2009年に制度化しました。
実は、日本で建てられている建物の大半は20〜30年でボロボロになってしまう、寿命の短い「使い捨て住宅」。
バブル期であれば、20〜30年が建て替えサイクルだったので、それでもよかったのでしょう。しかし、今の日本ではそういうわけにはいきません。
30年を超えて使わなければいけないのに、素材や躯体がボロボロになってしまう。そうして「使いたくても使えない」建物が増えたことが、昨今話題にのぼる「空き家問題」の一因となっています。
そういった短命な住まいの生産にストップをかけ「高耐久で長寿命な住まい」を普及させるために生まれたのが長期優良住宅。
今後の家づくりにおいて、確実に押さえておくべき基準です。

主な認定基準
日本における住宅の耐久性、維持管理の容易さ、環境負荷の低減などを目指して設定されている長期優良住宅。主要な認定基準は以下の通りです。
劣化対策
住宅の構造躯体の劣化対策として、例えば、木造の場合は防腐、防蟻処理が施されていることなどです。
耐震性
地震に対する安全性が確保されていること。具体的には、建築基準法で定める耐震基準の1.25倍の耐震性(耐震等級2以上)を持つことが求められます。なお、みらつぐ基準においては、耐震等級2は不十分という扱いです。詳しくは「04 耐震等級3」をご覧ください。
維持管理・更新の容易性
給排水設備や電気設備などがメンテナンスしやすい設計となっていること。後年、劣化した際に点検や交換ができなければ、長期にわたって住まうことはできません。
可変性
家族構成やライフスタイルの変化に対応できるような設計になっていること。これも、長く住まうために必要な措置と言えるでしょう。
バリアフリー性
高齢者や身体障害者が安心して住めるようなバリアフリー設計になっていること。これもまた、住まい手の将来的な暮らしに影響を与えるものです。
省エネルギー性
断熱性能や設備の省エネ性能が高く、エネルギー消費を抑える設計になっていること。暑い・寒いといった住まい手の身体的ストレスを軽減したり、光熱費を抑えたり、また環境負荷を下げることも、今後の住宅にとっては必要な要件です。
維持保全計画
長期的に住宅の維持保全を行うための計画が策定されていること。日本の住宅業界において、大きな問題は、実はここかもしれません。
数十年も使用する建物なのに、日本の住まいはこれまで一切の「定期点検」や「メンテナンス計画」がありませんでした。
定期的な点検や、修繕計画の立案実施が、長期優良住宅では定められています。